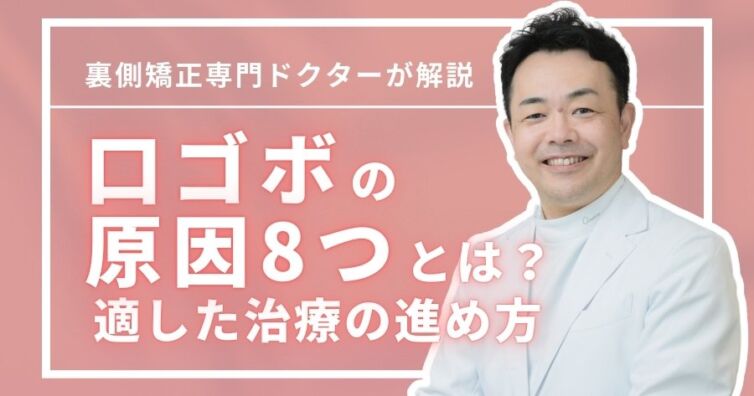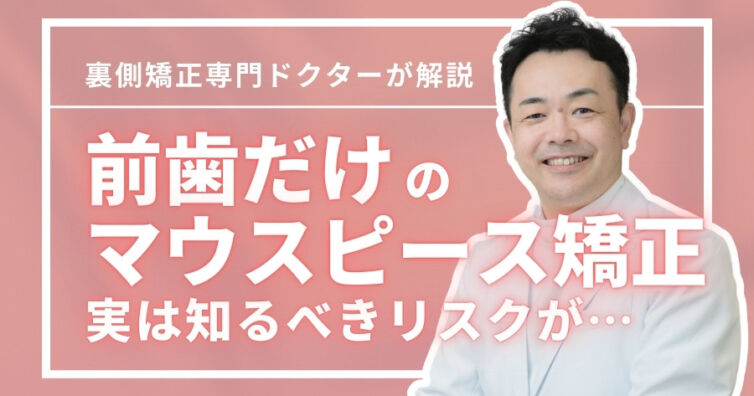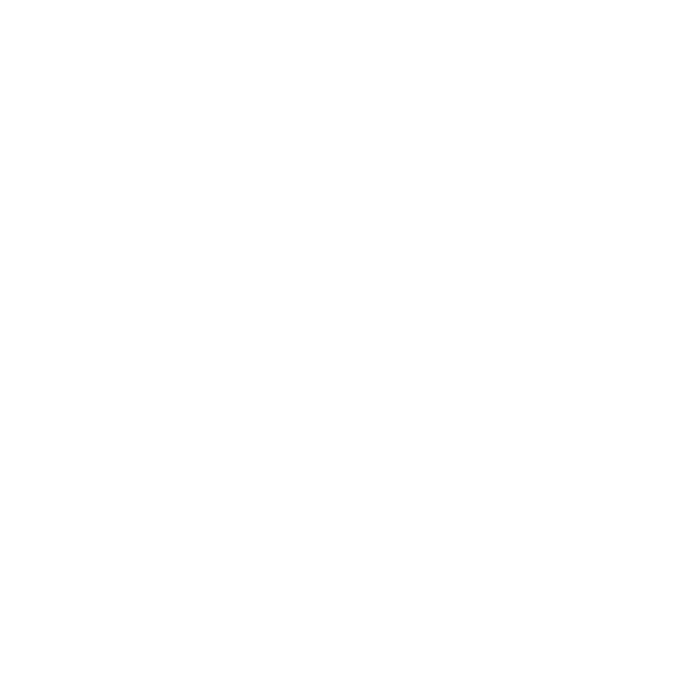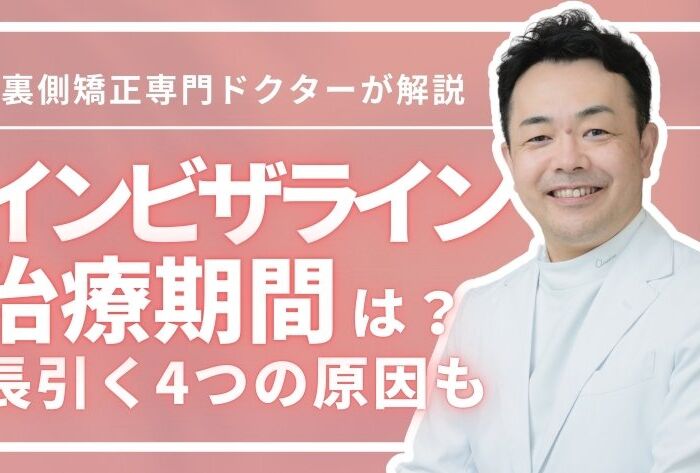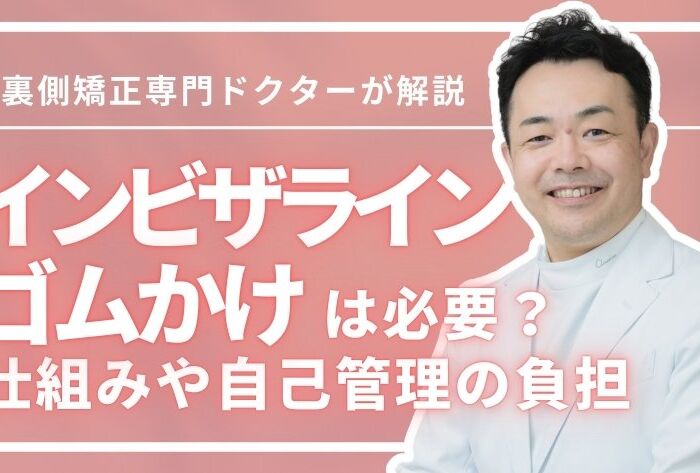「歯列矯正を始めたら、急に噛み合わせが悪くなった…」
「食事のときにうまく噛めない時期があって不安」
矯正治療中に、こうした悩みを抱える方は少なくありません。実際、「矯正中は噛み合わせが合わなくなる時期があるのが普通」と説明する歯科医院も多いでしょう。しかし、ここで重要なのは、噛み合わせが一時的に変化すること自体は自然なことですが、治療後半になっても噛み合わせが悪いままだとしたら、それには原因があるということです。
私は、25年以上にわたり歯列矯正治療に携わり、裏側矯正を専門に行ってきました。これまで多くの患者さんの治療に携わる中で、「矯正中に噛み合わない時期がある」のは事実ですが、その後スムーズに噛み合わせが整う人と、そうでない人には大きな違いがあることがわかっています。これを指摘する矯正歯科医は多くありません。
そこで本記事では、
✔ 矯正中に噛み合わせが一時的に合わなくなる理由
✔ 矯正の後半になっても噛み合わせが整わない人の特徴
✔ 正しい噛み合わせを取り戻すためのポイント
について詳しく解説していきます。
「矯正中の噛み合わせが不安」「このまま治療を続けて大丈夫なのか?」と感じている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
▼お急ぎの方は動画に概要をまとめましたのでご覧ください▼
も く じ
Toggle矯正中に噛み合わせが悪くなる本当の原因

歯列矯正を始めると、多くの患者さんが「矯正中は一時的に噛み合わせが悪くなるのは普通」とドクターから説明を受けるようです。たしかに、歯が動いている途中で噛み合わせが一時的にズレることはよくあることです。
しかし、治療の後半になると「噛み合わせのズレがすぐに解消する人」がいる一方で「長引いてしまう人」がいることを、多くの矯正歯科医は説明できていません。
実は、この違いを生む最大の要因は 、日常の中で歯にかかる余計な力なのです。矯正装置が正しく歯を動かしていたとしても、無意識の癖や生活習慣によって噛み合わせが崩れてしまうことがあるのですね。
以下によくある3つのケースをご紹介しましょう。
うつ伏せ寝・横向き寝が噛み合わせを崩す
日中は意識していても、寝ている間の姿勢はコントロールが難しいものです。特にうつ伏せ寝や横向き寝は、長時間にわたって歯や顎に余計な圧力をかけるため、噛み合わせに大きな影響を与えます。
たとえば、横向きに寝ると、片側の頬に圧がかかり、その力が歯をゆがませることがあります。うつ伏せ寝の場合、下顎が圧迫されて位置がズレたり、歯列全体に不要な力がかかったりすることで、歯の動きが不自然になり、噛み合わせが整いにくくなるのです。
この問題に気づいている矯正歯科医は多くありません。ドクターから患者さんに指導することも少ないのが現状です。しかし、長年、歯列矯正に携わってきた経験から確実に言えるのは、正しい姿勢を意識することで、矯正の効果を最大限に引き出しやすくなるということです。
頬杖や歯をずらすクセが噛み合わせを乱す
日常生活の中で何気なく行っている頬杖や片側噛みのクセも、噛み合わせのズレを引き起こす大きな要因です。
頬杖をつくと、顎に外から圧力がかかり、歯列が少しずつズレていきます。特に、いつも同じ側に頬杖をついている人は、噛み合わせが左右非対称になりやすくなります。なお、これは矯正治療中だけに限りません。頬杖の癖は、整った歯並びを維持するには害悪となる可能性が高いです。
また、食事の際に片側ばかりで噛むクセがある人も要注意です。左右の筋肉の発達に差が生まれ、顎のバランスが崩れることで、噛み合わせがズレる原因になります。
これらのクセは無意識に行ってしまいがちですが、歯列矯正中は特に意識して改善することが重要です。
舌の使い方が悪いと噛み合わせが乱れる
矯正治療では、歯の位置を整えることに注目しがちですが、実は舌の動きや位置も噛み合わせに大きく関わっています。
たとえば、歯列矯正をする患者さんの中には、知らずに舌で歯を押すクセがある人が少なくありません。舌で歯を押すと、歯が前方へ押し出され、治療計画とは異なる方向へ動いてしまうのです。こうしたクセは、意識的に改善し、トレーニングしないと治りません。
また、舌が正しい位置(上顎のスポット)にないと、噛み合わせが安定しづらくなることもあります。本来、舌は上顎に軽く触れているのが理想的な位置ですが、舌の位置が低いと、口呼吸が増え、歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼすのですね。
このような舌の悪いクセ(舌癖)は、矯正後の後戻りの原因にもなるため、MFT(口腔筋機能療法)を取り入れながら改善していくことが大切です。
矯正治療の後半で噛み合わせが良くならない人の特徴

矯正治療を進めると、前半では歯の移動に伴い一時的に噛み合わせがズレることがあります。しかし、後半に入ると、通常は噛み合わせが整い、安定していくものです。
ところが、先述したように一部の人は矯正治療の終盤になっても噛み合わせが良くなりません。とはいえ、具体的にどういう傾向の人がこうした問題に直面しやすいのか伝わりづらいと思いましたので、噛み合わせが良くならない人の特徴について、以下にまとめてみました。
歯に余計な力をかけ続けている
矯正後半で噛み合わせが整わない人の多くは、日常生活の中で無意識に歯に余計な力をかけ続けている ことがほとんどです。
以下のようなクセがある方は、せっかく整いつつある噛み合わせが崩れてしまうことがありますので特に注意してください。
- うつ伏せ寝・横向き寝を続けている
- 頬杖をつく習慣がある
- 舌で前歯を押すクセがある
- 片側ばかりで噛む習慣がある
これらのクセがあると、矯正装置が正しく歯を動かしていても、治療計画とは異なる方向に歯が動いてしまい、噛み合わせが乱れてしまいます。意外に思われるかもしれませんが、患者さん自身の生活習慣が原因で噛み合わせが崩れているケースがほとんどであることは、あまり指摘されていません。
しかし、まぎれもない事実なのです。
噛む習慣が足りず、咬筋が鍛えられていない
噛み合わせが整わない原因は、歯の動きだけではありません。しっかり噛む習慣がない人は、咬筋(噛むための筋肉)が鍛えられず、噛み合わせが不安定になりやすいのです。
本来、食事の際にしっかり噛むことで、顎の筋肉が鍛えられ、噛み合わせが自然に安定していきます。しかし、矯正中に「噛みづらいから」と柔らかいものばかり食べたり、片側でしか噛まなかったりすると、筋肉のバランスが悪くなり、噛み合わせがズレる原因になってしまうのですね。
特に以下のような人は、矯正後半になっても噛み合わせが安定しにくい傾向があります。
- 矯正治療中、あまり噛む習慣がなかった
- 柔らかいものばかり食べていた
- 片側だけで噛むクセがある
咬筋がしっかり働くことで、歯は自然と噛みやすい位置に落ち着くものです。噛み合わせを安定させるためには、「噛む」という行為を意識的に増やすことが重要です。
矯正後半になれば、本来は噛み合わせが整うはず
矯正治療の終盤に入ると、歯並びがほぼ整い、噛み合わせも安定していくのが一般的です。歯が正しい位置に収まれば、自然に上下の歯がフィットするようになり、違和感もなくなっていきます。
しかし、噛み合わせが整わないまま治療が進んでしまう人は、日常生活の中での悪習慣が原因になっていることが99%といえます。経験値の豊富なドクターであれば、患者さんの傾向からそうした悪習慣を推測できますが、経験値が低かったり、技術の低いドクターだと気づけません。
この記事を読んで頂いているあなたは、ご自身が把握するだけでも結果は違ってくると思います。矯正後半になっても噛み合わない時期が続くのであれば、以下を疑ってください。
- 矯正の終盤になっても噛み合わせが悪いのには、何らかの力が歯にかかっているはず。
- 正しい筋肉の使い方ができていないと、矯正後半でも噛み合わせがズレたままになる。
- 矯正が進めば自然に噛み合わせが整うはずだが、それを邪魔する要因が日々の生活習慣や舌の癖などに必ずある。
本来は、担当の矯正歯科医が指摘すべきことですが、よほど経験値がないとそうはいきません。すべての装置調整をドクター自らが行わないとわからないことでもあります。
とにかく、歯に余計な力をかけない生活習慣を身につける意識とトレーニングが必須であることを覚えておいてください。
セレーノ矯正歯科医院で「途中で噛み合わせが悪くなる」と伝えない理由
実は当院では、矯正治療を進める際に、途中で噛み合わせが悪くなるという説明をあえてしていません。その理由は、患者さんが「これは普通のこと」と思ってしまい、間違った力のかけ方を続けてしまうリスクがあると考えるからです。
矯正中の一時的な噛み合わせのズレは、確かに起こり得ることですが、患者さん自身の生活習慣が原因でズレてしまうケースの方が圧倒的に多いのも事実です。「矯正中は噛みづらいのが普通」と思い込むことで、悪い癖を続けてしまったり、うつ伏せ寝や頬杖などの悪習慣が、噛み合わせのズレを悪化させてしまったりしかねません。
これを防ぐために、当院では噛み合わせを崩す原因を患者さん自身が作っていることが多いという視点を持ってもらうことを大切にしています。歯列矯正治療は、患者さんの協力があってこそ成功するもの です。正しい噛み方や生活習慣を身につけることが、矯正後の理想的な噛み合わせだけでなく、ナチュラルで美しい口元になるためにも大事なことなのです。
正しい噛み合わせを取り戻すための改善策

ここまで読んで頂いたあなたには、最良の矯正治療の結果を手にして、思い切り笑顔で笑ってほしいので、たとえ担当のドクターが噛み合わない時期が続く原因を正しく指摘できなくても、ご自身で改善できる方法をお伝えします。
まずやるべきことは「噛み合わせを崩す原因を取り除く」ことです。噛み合わせが乱れるのには明確な理由があり、それを改善しなければ、矯正の最終段階になっても理想的な仕上がりにはなりません。
矯正装置だけで完璧な噛み合わせができるわけではなく、患者さん自身の協力が結果を大きく左右します 。特に普段の生活習慣が噛み合わせに与える影響は非常に大きいため、悪い癖をやめることが矯正治療の良い結果とするためのカギとなります。
うつ伏せ寝・横向き寝をやめる
もし、寝入る前にうつ伏せ寝・横向き寝の習慣があるのであれば、やめてください。
先述したように、寝ている間に頭の重みが片側の頬や顎にかかることで、歯や顎に余計な圧力がかかり、歯列がズレる原因になります。特に、矯正中は歯が動きやすい状態にあるため、この影響を受けやすく、朝起きたときに「噛み合わせが変わった気がする」と感じることがあるかもしれません。
改善策としては、シンプルですが、仰向けで寝る習慣をつけること。枕の高さを調整し、仰向けで寝やすい環境を整えるだけでも、噛み合わせへの悪影響を減らすことができるはずです。
頬杖をやめる
寝る姿勢と同様に、頬杖は、噛み合わせのバランスを崩す大きな原因のひとつです。
片側の顎に継続的に圧力がかかることで、歯が傾いたり、顎の位置がズレたりすることがあるため、矯正中は特に注意が必要です。頬杖をつくクセがある人は、無意識のうちに噛み合わせを崩している可能性があります。
デスクワークやスマホを使うときなど、無意識に頬杖をついていないか意識し、なるべく姿勢を正すことを心がけることで、改善していきましょう。
歯をずらす・押す癖をなくす
矯正中に歯を意識的に動かそうとしたり、舌で押したりすることは、治療計画とは異なる方向に歯が動く原因になります。
特に、舌で前歯を押す癖や、奥歯をずらして噛む癖がある人は、矯正がスムーズに進まないことが多いので、くれぐれもご注意ください。無意識に動かしてしまう場合、ごく身近な人がいれば、逐一、指摘してもらうのが良いでしょう。これらの癖を改善することで、矯正の仕上がりが本当に、美しくなります。
ここでは詳しくお伝えしませんが、舌の使い方が気になる場合は、MFT(口腔筋機能療法)を取り入れるのが有効です。正しい舌の位置を意識することで、歯並びや噛み合わせがより安定しやすくなります。ただし、矯正歯科医や歯科衛生士の専門的な指導やアドバイスを得て、習慣化してください。
噛み合わせを整えるには、咬筋を鍛えることも大切
噛み合わせを改善するためには、「正しい力をかける」ことも重要です。矯正中に食事の際にあまり噛まなくなると、咬筋(噛むための筋肉)が弱まり、噛み合わせが不安定になってしまうことがあります。
よく噛む習慣をつける(意識的に咬筋を使う)
噛み合わせを安定させるためには、当たり前のことをいうようですが、食事の際にしっかりと噛む習慣をつけましょう。矯正中は「食べにくいから」と柔らかいものばかり食べてはいけません。かといって、固いものばかりもよくありませんが、どんな食事でも、しっかり噛むことで、歯が正しい位置に落ち着きやすくなります。
食事の際に左右均等に噛む
片側だけで噛むクセがあると、顎の筋肉のバランスが崩れ、噛み合わせにも影響が出ることがあります。食事の際には、左右の歯でバランスよく噛むことを意識しましょう。矯正中は一方の歯でばかり噛んでしまうことも多いため、意識的に両側を使うようにしてください。
まとめ|矯正治療中の噛み合わせの変化を正しく理解しましょう

矯正治療中に噛み合わせが悪くなるのは、一時的な変化であることがほとんどですが、治療の後半になっても改善しない場合は、何らかの原因があるということが伝わりましたでしょうか。
噛み合わせが整いにくい人の特徴として、うつ伏せ寝や横向き寝、頬杖、舌のクセなど、日常の何気ない習慣が影響していることが多いという事実は、意外と知られていません。矯正装置が歯を正しい位置へ動かしているにもかかわらず、こうした悪い習慣によって歯に余計な力がかかると、思うように噛み合わせが改善されないことがあります。
また、 咬筋(噛む筋肉)をしっかり使えていないと、噛み合わせが安定しにくくなるため、食事の際には意識的に噛む回数を増やし、左右均等に噛むことを心がけてください。矯正治療がスムーズに進んでいる人と、なかなか噛み合わせが整わない人の違いは、こうした意識と生活習慣の差によって生まれます。
歯列矯正は、歯科医の技術だけでなく、患者さん自身の協力が結果を左右する治療です。治療が進んでも噛み合わせがなかなか整わない場合は、「日々の習慣の中に原因がないか?」を見直してみることが、理想的な仕上がりへの近道になるでしょう。
「噛み合わせが悪い時期はあるもの」と思い込むのではなく、どうすれば噛み合わせをより良くできるのか?という視点で、自分の生活習慣を意識してみてください。
あなたの矯正治療が、より良い結果につながりますように。そして、とびきりの笑顔で笑えますように。