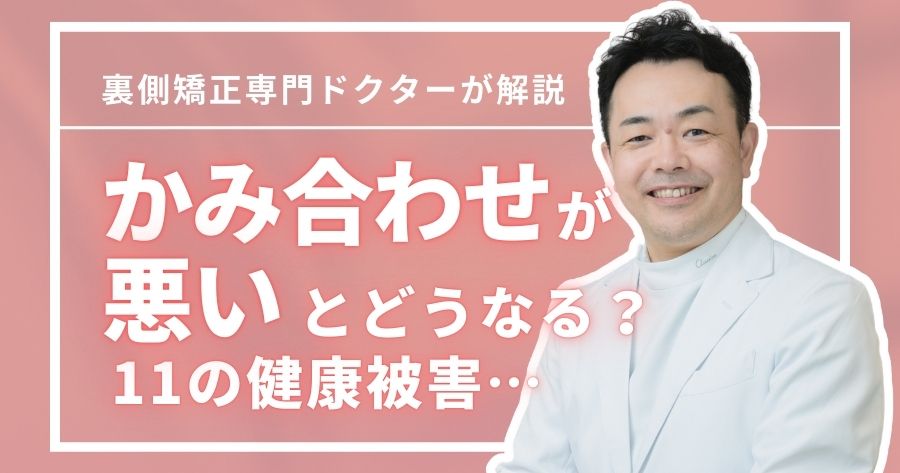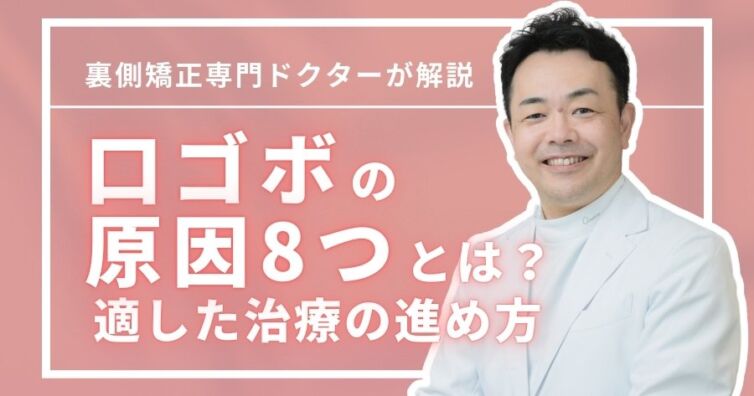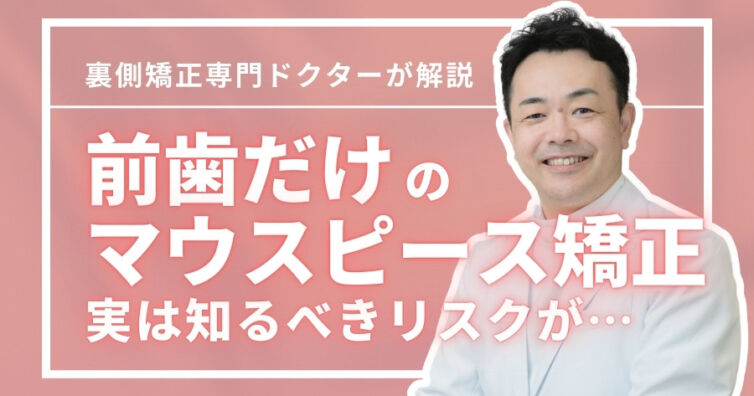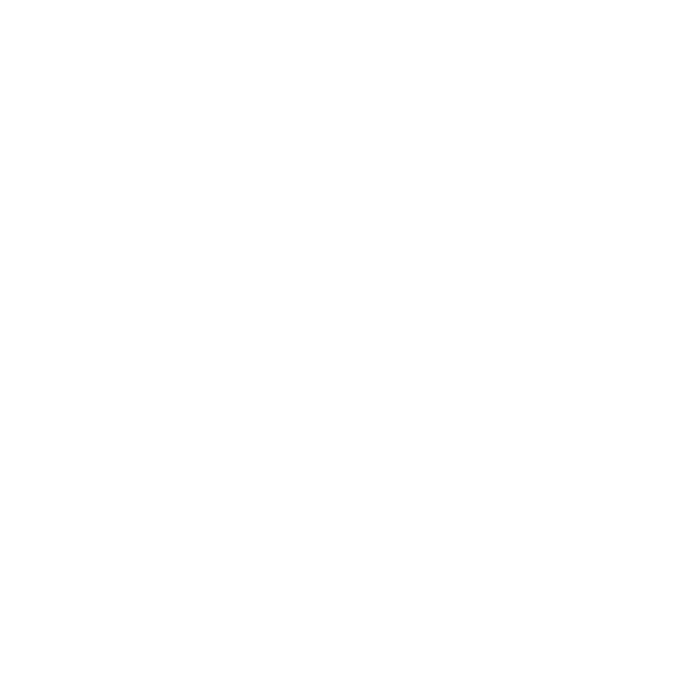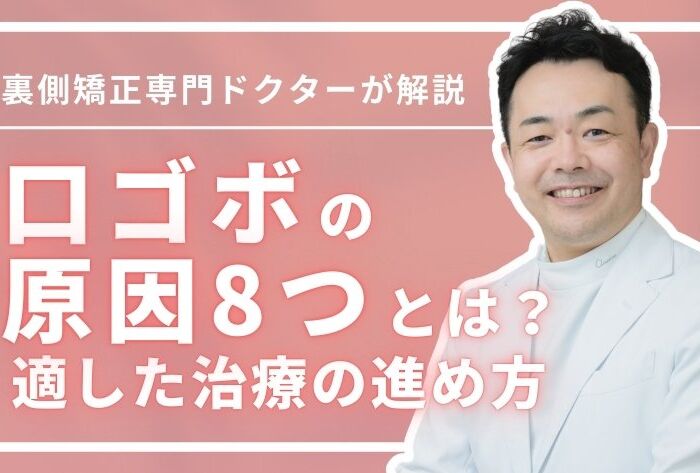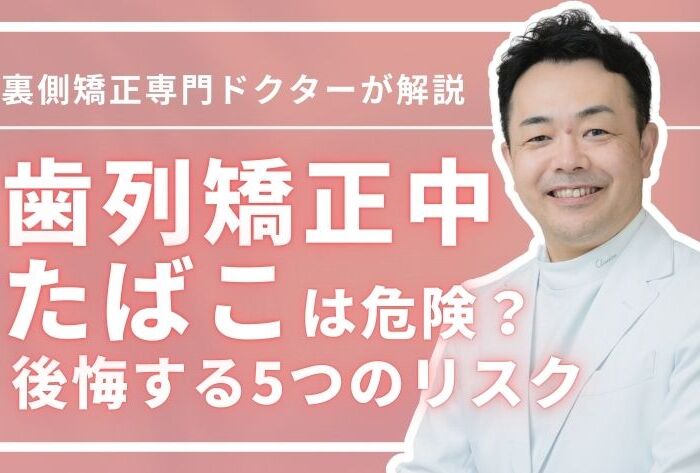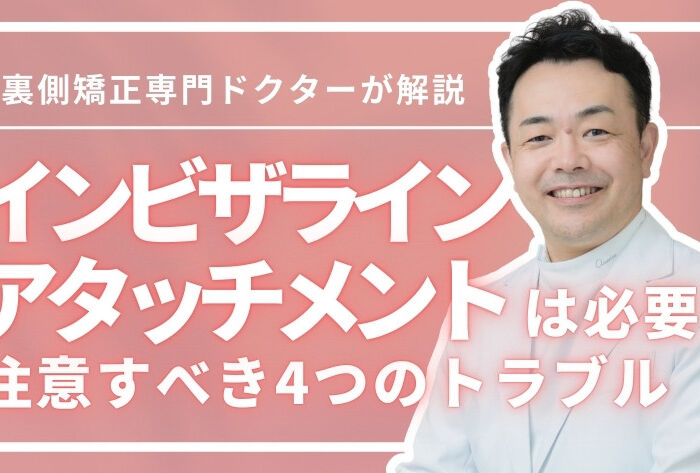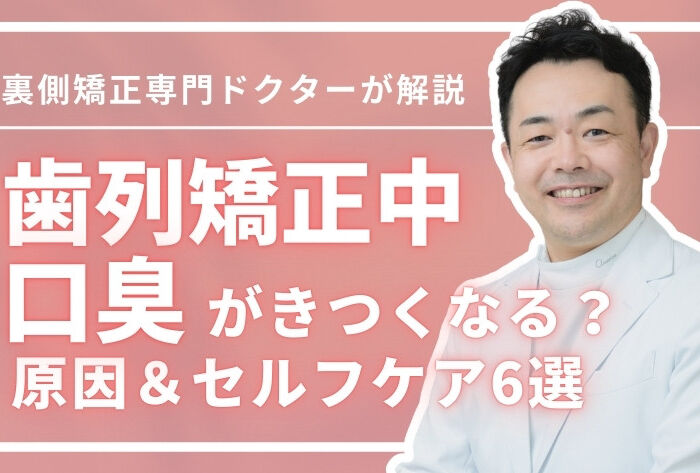「時々、顎に痛みや違和感が…」
「食事のとき何か疲れやすいな…」
「左右の顔が少し違う気がする…」
あなたも同じような悩みを抱えていませんか?「歯のかみ合わせが悪いのでは…」と思いながらも、ついつい後回しにしている方も多いと思います。
私は25年以上の経験を持つ矯正歯科医として、数多くの患者さんを診療しています。初期症状を見過ごすことで生じる様々なリスクを見てきたからこそ、早期に気づいて対処する大切さを強く感じています。
この記事では、歯のかみ合わせが悪いとはどういう状態なのか、そしてそれが招く健康被害などを詳しくお話しします。あなたの小さな悩みが大きな問題になる前に、今できることを一緒に学んでいきましょう。
▼お急ぎの方は動画に概要をまとめましたのでご覧ください▼
も く じ
Toggle歯のかみ合わせが悪いとはどういう状態?

歯のかみ合わせが悪いとは、上下の歯が正しく接触していない状態を指します。歯科医学では、このような状態を「不正咬合(ふせいこうごう)」と呼びます。
正常なかみ合わせでは、奥歯でしっかりとかみ締めたときに、上の前歯が下の前歯より2~3mm程度前に出て、上下方向には2~3mm程度重なって、上の歯が下の歯を適度に覆います。
正常なかみ合わせとの違い
かみ合わせが悪い状態では、理想的な歯の位置関係が保てません。
例えば、上下の前歯がぶつかって奥歯が浮いてしまったり、逆に奥歯は接触しているのに前歯に隙間ができたりします。当院でも、このような症状で悩む方から多くのご相談をいただいています。
正常なかみ合わせと問題があるかみ合わせの違いを、下記でわかりやすく比較してみましょう。
| 項目 | 正常な状態 | 問題がある状態 |
|---|---|---|
| 前歯の重なり具合 | 少し重なる(2~3mm) | 重なりすぎ/隙間が空く |
| 奥歯の噛み具合 | 左右均等に噛める | 片側に偏って噛む |
| 顎の位置 | まっすぐ安定している | 左右にずれている |
こうした違いを理解しておくことで、あなた自身のかみ合わせを理解する手がかりになるはずです。
かみ合わせの問題パターン
歯のかみ合わせの悪さには、いくつかの典型的なパターンがあります。以下の症状に心当たりがある方は、かみ合わせに問題がある可能性が高いでしょう。
| パターン | 状態 |
|---|---|
| 出っ歯(上顎前突) | 上の前歯が前に出ている |
| 受け口(下顎前突) | 下の歯が上の歯より前 |
| 開咬(オープンバイト) | 上下の前歯に隙間ができる |
| 過蓋咬合(ディープバイト) | 上の前歯が下の前歯を深く覆う |
| 交叉咬合(クロスバイト) | 一部の歯が上下逆に噛み合う |
これらのパターンは単独で起こることもあれば、複数が組み合わさって現れることもあります。診断により、あなたがどのタイプに当てはまるかを把握することで、適切な治療方法を選択できるでしょう。
>>>オープンバイトの矯正は難しい?原因&放置の危険と失敗しないコツ
>>>ディープバイト矯正での治し方!6つの原因&早めに矯正すべき理由
簡単なセルフチェック方法
参考に、自宅でもできる簡単なかみ合わせのチェック方法をご紹介します。鏡の前で以下の項目を確認してみてください。
| チェック | 確認内容 | 正常な状態 |
|---|---|---|
| □ | 口を軽く閉じる | 上下の唇が自然に合う |
| □ | 食べ物を噛む | 左右どちらかに偏らない |
| □ | 口を大きく開ける | 顎がまっすぐ動く |
| □ | かみ合わせる | 顎に違和感や痛みがない |
| □ | 前歯の見た目 | 極端な出っ歯や受け口がない |
※注意:これらのチェック項目は参考程度に留めていただき、詳しい診断は必ず歯科医師にご相談ください。
チェックしてみていかがでしたか?1つでも「あれ?」と思う項目があれば、注意が必要なサインかもしれません。小さな違和感の内に、早めのタイミングで対処することが大切です。
以上、歯のかみ合わせが悪い状態について、基本的な特徴からチェック方法まで解説しました。あなたの状況と照らし合わせて、心配な点があれば歯科医師の診察を検討してみて下さい。
かみ合わせの悪さが招く11の健康被害

実は、歯のかみ合わせが悪いことで起こる健康への影響は想像以上に広範囲に及びます。単なる歯の問題にとどまらず、体全体に様々な症状を引き起こすことがわかっています。
ここでは、かみ合わせの悪さが招く11の主要な健康被害について詳しく解説します。
虫歯や歯周病
かみ合わせが悪いと、虫歯や歯周病のリスクが高まります。歯並びの乱れによって歯ブラシやフロスが届きにくい箇所が多くなるためです。
歯の隙間の食べカスをうまく清掃できないと、口腔内の健康状態は著しく悪化します。定期的な歯科検診を受けていても、根本的なかみ合わせの問題を解決しない限り、虫歯や歯周病を繰り返す可能性が高いのです。
顎関節症
顎関節症は、かみ合わせが悪い方にも多く見られる症状です。顎の関節に負担がかかり続けることで、痛みや機能障害が生じる恐れがあります。
【顎関節症の典型的な症状】
- 口が大きく開けられなくなる
- 口を開ける時に顎関節が痛む
- 口の開閉時にカクカクと音がする
- 急に口が開かなくなることがある
ストレス、歯ぎしり、外傷などと組み合わさることで症状が悪化しやすく、放置すると日常生活に大きな支障をきたす恐れがあります。
頭痛・肩こり
意外かもしれませんが、歯のかみ合わせの悪さは頭痛や肩こりの原因にもなります。顎の筋肉と頭部・首の筋肉は密接に関連しているためです。
【頭痛・肩こりが起こる例】
- 咀嚼筋に過度な負担がかかる
- 側頭筋の緊張が頭痛を引き起こす
- 首や肩の筋肉にも負担が波及する
頭痛薬や湿布で一時的に症状が改善しても、原因が歯のかみ合わせにある場合は、症状が繰り返し現れることが多いです。
消化不良
歯のかみ合わせが悪いと、消化の第一段階である食べ物を十分に咀嚼できないため、胃腸への負担が増える場合があります。
食べ物が大きいまま胃に送られることで胃での消化に時間がかかり、また十分に噛めないことで唾液と食べ物が混ざりにくく、消化効率が低下する恐れがあります。
食事を楽しめないだけでなく、胃もたれや胸やけに悩まされている方は、かみ合わせが原因の1つかもしれません。
顔や姿勢の歪み
かみ合わせの悪さから、かみやすい側ばかりを使う癖がつき、顔の筋肉の発達に左右差が生まれます。この影響は輪郭の非対称にもつながります。
筋肉の偏った使い方は、場合によって首や肩の位置のずれも引き起こします。こうした変化は年齢を重ねるにつれて、より顕著になる傾向があり、顔の左右差は多くの方にとって大きな悩みの種となるでしょう。
滑舌の悪さ
正しい発音には、歯と舌の適切な位置関係が不可欠です。かみ合わせが悪いとこの関係が崩れ、滑舌に影響を与える場合があります。
【滑舌が悪くなりやすい音】
- サ行:歯と舌の隙間から空気が適切に通りにくい
- タ行:舌の先を上前歯の裏側に正確に当てることが難しい
- ラ行:舌の動きや位置が制限されやすい
仕事でのプレゼンや人とのコミュニケーションにも影響を及ぼすことがあります。例えば、相手に聞き返されることが多い方は、歯のかみ合わせが原因の1つかもしれません。
ストレス
歯のかみ合わせが悪いことで生じる様々な不快症状は、精神的なストレスの原因にもなります。
- 食事を楽しめないストレス
- 慢性的な痛みによるイライラ
- 見た目への不安やコンプレックス
など、複数の要因が重なることで精神的な負担が増加します。さらに、ストレスが蓄積することで歯ぎしりや食いしばりが起こり、悪循環に陥ってしまう方も多いでしょう。このような状態が続くと、日常生活の質にも大きく影響してしまいます。
耳鳴り・めまい
顎関節は耳の近くに位置しているため、かみ合わせの問題が耳の症状として現れることがあります。耳鳴りやめまいはその症状の1つです。
筋肉の緊張が耳管の働きに影響を与えたり、顎関節の異常が周辺組織に影響することで、症状を引き起こす場合があります。
ただし、耳鳴りやめまいには様々な原因があるため、まずは耳鼻科での詳しい検査が重要です。原因が特定できない場合に、歯のかみ合わせとの関連を疑うことがあります。
集中力の低下
慢性的な痛みや不快感は、集中力の低下を招きます。また、十分に噛めないことで咀嚼による脳の活性化効果が得られにくいことがあります。
口元への違和感や不快感で意識が散漫になり、本来の能力を発揮しにくい方も多いです。さらに、食事に時間がかかったり、疲れやすさを感じることで、日常のリズムに乱れが生じることもあるでしょう。
これは仕事や勉強の効率にも大きく関わってくる問題です。「なぜか集中できない…」と感じている方は、歯のかみ合わせが原因の1つかもしれません。
口呼吸
「口呼吸がなぜダメなの?」という方も多いですが、実は健康への悪影響が多くあります。かみ合わせの悪さは顎や口周りの筋肉のバランスに影響し、それが口呼吸を引き起こす場合があります。
口呼吸により口の中が乾燥すると、唾液の抗菌作用が低下して細菌が繁殖しやすくなり、虫歯や歯茎の炎症、口臭が起こりやすくなります。また、鼻でのフィルター機能が働かないため、風邪などにかかりやすく、のどの痛みや違和感も生じやすい傾向があります。
口は本来、食事や発声のための器官であり、呼吸については鼻呼吸が基本です。口呼吸が習慣化すると、舌の位置が下がり、筋肉が弛緩してフェイスラインや口周りのたるみを引き起こす恐れもあります。
姿勢の悪化
歯のかみ合わせが悪いと咀嚼筋などに緊張が生じ、頭部の傾きや位置に変化が起こる恐れがあります。それを補うために背骨全体のバランスが変わり、全身の姿勢が悪くなる場合も少なくありません。
良い姿勢は健康の基本であり、見た目の印象にも大きく関わります。姿勢の悪さを指摘されたことがある方は、かみ合わせが影響している可能性も考えられるでしょう。
以上、歯のかみ合わせが悪いことで起こりうる11の健康被害について解説しました。
私の経験から言えるのは、これらの症状は単独で現れることもあれば、複数が同時に起こることもあります。思い当たる症状がある方は、かみ合わせの問題が関わっている場合も多いため、歯科医師に一度ご相談されることをおすすめします。
なぜ歯のかみ合わせは悪くなる?原因とは

歯のかみ合わせが悪くなる原因は多岐にわたります。日常の生活習慣から遺伝的な特徴まで、様々な要素が絡み合って現在の状態を作り出しているのです。
原因を正しく理解することで、予防や改善への道筋が見えてきます。ここでは、かみ合わせが悪くなる主な原因について詳しく解説していきます。
日常生活の習慣による原因
日常生活での様々な習慣は、歯のかみ合わせを悪化させる大きな原因となります。特に、子どもの頃の癖は成長期の顎や歯に強い力を加えます。
| よくある癖 | どこに影響する? | 起こりやすい問題 |
|---|---|---|
| 指しゃぶり | 前歯 | 前歯が前に出る・隙間ができる |
| 舌を前に出す | 前歯・奥歯 | 上下の歯が全体的に噛み合わない |
| 口で息をする | 口周り全体 | 歯列が狭くなり正しく噛み合わない |
| 頬杖をつく | 片側の顎・歯列 | 片側の歯並びが内側に傾く |
| 片方だけで噛む | 顎・歯 | 左右のかみ合わせが不均等になる |
大人になってからも、ストレスによる歯ぎしりや食いしばり、悪い姿勢での長時間作業などが、かみ合わせをさらに悪化させる場合が多いです。
現代社会では、柔らかい食べ物が中心となり、しっかりと噛む機会が減っています。このことも顎の発育不足を招き、歯が並びきらない一因となっているのです。
さらに、虫歯や歯周病による歯の喪失、不適切な歯科治療なども、かみ合わせのバランスを崩す原因となります。一度バランスが崩れると、他の歯にも負担がかかり、問題が連鎖的に拡大していく傾向があります。
遺伝的な原因と成長過程での変化
かみ合わせの問題には、遺伝的な原因と成長過程での環境的な変化も関わっています。
遺伝的原因では、顎や歯の大きさ、歯の本数などが親から子へと受け継がれます。その一例を挙げると、小さな顎に大きな歯が生えてくると、歯が並びきらずにかみ合わせが悪くなってしまうのです。
| 遺伝的原因 | 起こりやすい問題 |
|---|---|
| 顎が小さめ | 歯がきれいに並ばない |
| 歯のサイズが大きい | 歯が重なってガタガタになる |
| 生まれつき歯が足りない/多い | 隙間ができる/詰まりすぎる |
| 上下の顎の成長バランスが悪い | 出っ歯や受け口になる |
また、成長期の栄養状態や病気、家族で共通する生活や食習慣、さらには子どもが親の悪癖を真似するなども大きく関係しています。
その他、乳歯から永久歯への生え変わりの時期にトラブルがあると、将来のかみ合わせに深刻な影響を与える可能性が高いため、この時期の管理はとても重要です。
外傷や病気による原因
事故やケガによる外傷も、かみ合わせが悪くなる原因の1つです。スポーツ中の衝突や転倒、交通事故などで顎や歯に強い力が加わると、以下のような問題が起こりやすいです。
| 原因 | 何が起こる? | 起こりやすい問題 |
|---|---|---|
| 顔のケガ | 歯や顎の骨が傷つく | 歯がずれる・骨が変形する |
| 顎のケガ | 関節や筋肉が傷つく | 口が開けにくい・痛みが出る |
また、病気が歯や顎の発育に関わる場合もあります。例えば、成長に関わるホルモンや筋肉の病気などが顎の成長や噛む筋肉に影響し、結果としてかみ合わせの問題を引き起こすことがあります。ただし、これらは比較的稀なケースです。
以上、歯のかみ合わせが悪くなる様々な原因について解説しました。かみ合わせの問題は、根本原因に基づいた治療計画が重要です。気になる症状がある方は、まず詳しい診断や検査の実施をおすすめします。
歯の悪いかみ合わせは今すぐ治療すべき?

結論から言うと、症状や生活への影響によって判断が分かれるところです。緊急性の高いケースもあれば、タイミングを見計らってもよいケースもあります。
ここでは、今すぐ治療すべきかどうかの判断基準について解説します。
今すぐ治療が必要なケース
かみ合わせが悪い状態の中でも、以下のような症状の場合は早期の治療をおすすめします。これらの症状は、放置するとより複雑な治療が必要になる可能性が高いためです。
【すぐに治療を始めるべき症状】
- 食事に支障がある(うまく噛めない)
- 顎関節症の症状がある(顎の痛み、音がする、口が開けにくい)
- 歯ぎしりや食いしばりが激しい
- 歯の摩耗や破損が進んでいる
- 発音に明らかな問題がある
- 顔や姿勢の歪みが進行している
- 見た目のコンプレックスが強く、仕事や人間関係に支障がある
これらに当てはまる場合は、症状の程度に応じて、早めに治療時期を検討することが大切です。中でも顎関節症の症状がある方は要注意です。痛みが続く場合や口の開閉に制限がある場合は、専門医による正確な診断と治療が重要です。
緊急性の低いケースでの対応
一方で、緊急性が低い場合は、定期的な観察を行いながら、治療の適切なタイミングを見極めることも可能です。ただし、「経過観察」は「放置」とは異なります。
軽度のかみ合わせの問題であっても、将来的には治療が必要なことはよくあります。歯科検診を受けながら、状態の変化を注意深く観察することが大切です。
【経過観察中に注意すべきポイント】
- 症状の悪化がないか定期的にチェックする
- 新たな不快症状が現れていないか確認する
かみ合わせの問題は自然に改善することは少なく、年齢とともに治療が複雑になる恐れもあるため、適切なタイミングでの治療の検討が大切です。
「今すぐ治療すべきか?それとも様子を見るべきか?」で迷っている方は、自身で安易な判断はせず、信頼できる歯科医師のカウンセリングで相談することをおすすめします。
当院セレーノ矯正歯科の症例紹介
実際に当院で治療を行った症例をいくつかご紹介いたします。治療前後の変化をご覧いただき、矯正治療の可能性を感じていただければと思います。



いかがでしたか?「私もこんな風に変われるかもしれない」と少しでも感じていただけたでしょうか。
私たちが大切にしているのは、どうしてそのような歯のかみ合わせになったかを徹底的に調べることです。日頃の習慣や無意識に行っている癖まで詳しく分析し、患者さんと一緒に治療に取り組むことで、より確実で根本的な改善を心がけています。
当院セレーノ矯正歯科は、さいたま市内で「裏側矯正」を専門に行う医院として、周りの目を気にせずに治療を進めたい方のニーズにお応えしています。「装置が見えるのが恥ずかしくて…」と諦めかけていた方に、より良い選択肢をご提供できます。
※矯正治療の結果には個人差があります。
まとめ:歯の悪いかみ合わせは早めの治療を

かみ合わせの問題は、まるで静かに進行する病気のようなものです。最初は「ちょっと気になる程度」だったものが、気づいた時には日常生活に大きな影響を与えている…そんなケースを数多く見てきました。
あなたが感じている「なんとなくの不調」も、もしかすると歯のかみ合わせが関係しているかもしれません。かみ合わせが悪い状態を改善することで期待できる変化は、想像以上に大きなものです。
【かみ合わせ改善で期待できる変化】
- 食事がおいしく楽しく感じられる
- 左右どちらでもバランスよく噛める
- 口をしっかり閉じられるようになる
- 硬い物でも遠慮なく噛めるようになる
- 自然な笑顔に自信が持てるようになる
- 将来的な歯の健康を守ることができる
「でも、矯正治療って目立つしイヤかも…」そんな心配をお持ちの方にこそ知っていただきたいのが、「裏側矯正」という選択肢です。装置がほとんど見えないため、周囲の見た目を気にせず歯並びの改善を目指すことができます。
当院では「もっと早く治療を始めていれば」という声をよく耳にします。会話に集中できる、鏡を見るのが楽しい、口の開閉がしやすい、イライラが減る、そんな快適さを手に入れることで、生活の質も向上するでしょう。
もしこの記事を読んで「当てはまる症状がいくつかある」と思われたなら、それは改善への第一歩を踏み出すサインです。1人で悩み続けるよりも、まずは矯正歯科での詳しい診断をおすすめします。
あなたが毎日を快適に過ごせるその日のために、私たちセレーノ矯正歯科が全力でサポートいたします。小さな一歩が、きっと大きな変化につながるはずです。